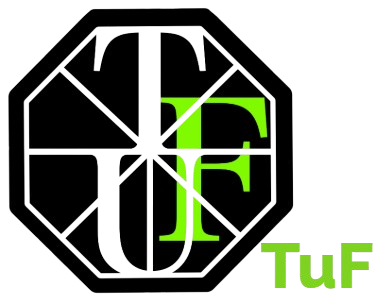最近の主な動向・課題
倒産・休廃業件数の増加・経営悪化
2024年における介護事業者の休廃業・解散件数は 612件 に達し、前年(510件)から約2割増加。内訳では訪問介護事業が448件と7割超を占める。
2025年上半期(1〜6月)では、訪問介護事業者の倒産件数が 45件(負債1,000万円以上)と、2年連続で過去最多を更新。従業員10人以上や負債額1億円以上の案件も増えてきている。
経営実態調査では、介護サービスを提供する事業所の平均利益率(収支差率)が2.4%と、前年度より0.4ポイント悪化。特養・老健などでは、介護保険制度開始以来初めてマイナス収支の施設も。物価高騰などが主な要因とみられる。
事業者倒産・経営難の背景には、人手不足・賃金上昇・光熱費などコスト高、そして介護報酬の見直しが影響しているとの声が強い。
これらは、特に規模の小さい事業所や訪問介護主体の事業者に深刻な影響を与えているようです。
人手不足・処遇改善のプレッシャー
介護施設・事業所の多くが “人手不足” の状態を訴えており、約70%の介護サービス事業所が労働力不足を自覚しているという調査もある。
労働力確保の観点から、外国人介護人材の採用・育成を進める動きが加速している。例えば、Sompo Care がインドに介護研修センターを設け、将来的に日本国内で就労できるようにする取り組みを始めている。
また、介護福祉士国家試験において「パート合格制度」の導入構想が出ており、全科目一度に合格する必要を緩和し、分割合格などを可能にする制度変更で人材流入を促す狙いも。
制度・政策対応と将来戦略
経済産業省(METI)は「高齢者介護・介護関連サービス産業を地域ごとに持続可能な形で発展させる戦略」を議論する研究会を設け、2040年に向けた方向性を整理する報告をまとめている。経済産業省
新たに、介護サービス事業者に対して 財務諸表 (損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書など) を含む経営情報の公表を義務付けるルールが打ち出されており、透明性向上と経営責任の強化が狙われている。
テクノロジー・DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入も注目されており、業務効率化・介護負荷軽減を目指す試みが各所で進んでいる。Sompoグループの「Mirai no Kaigo(未来の介護)」プロジェクトなどがその一例。
介護報酬引き下げの影響・現状調査
訪問介護において、基本報酬が 2%程度引き下げられたことが報じられ、その影響で利益率が非常に厳しくなった事業所もあるという声が現場から挙がっている。
政府・厚労省も、この報酬改定の実際の影響を把握するため、調査を実施しているという報道がある。
ケアマネジャーの業務整理・見直し
厚生労働省は、ケアマネジメント業務に関する課題を整理する検討会を設け、業務の類型化や業務外業務の他機関への引き継ぎなども議論されている。
こうした動きは、ケアマネジャーの業務負荷軽減や効率化を意図するもので、現場との乖離・調整が重要なテーマになっている。